文化財
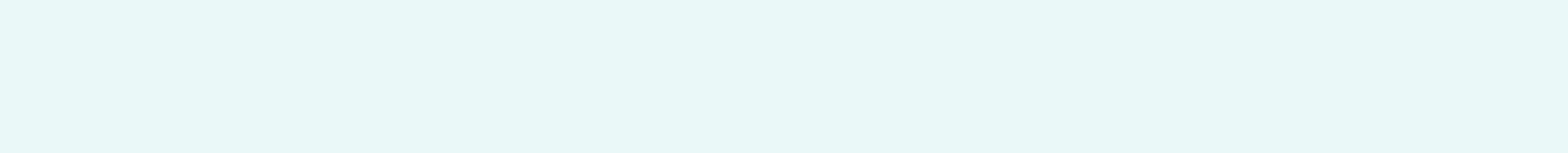
茂林寺の閻魔王像 1躯
本像は像高101.3㎝、等身大を越える法量をもち、頭部に大きく重たげな冠をいただき、眉をつり上げ両眼を見開き口を大きく開けて舌先を覗かせた激しい忿怒の相を表す通例の閻魔王像である。修理前は頸部左右の部材が欠失していたため、頭部が沈み込みバランスの崩れた姿であったが、適切な処理によって本来の安定感のある威容が回復された。頭部過大で類型化、誇張化のめだつ表現様式は、その規格的な木寄せ法とともに江戸時代の製作であることを物語っている。修理によって、表面の彩色に新旧の二層あり、彩色に修理の手が加わっていること、また、台座の裏面に天明2年(1782)、江戸浅草田原町の大仏師三上喜八の墨書銘があることが明らかとなった。
東京芸術大学教授、長澤市郎氏の所見では、江戸期の閻魔王像としては品のよい造形表現と丁寧な彩色から実際の造立時期はさかのぼり、天明二年の墨書銘は修理時のものであると考えられる。大きな冠を除けば、正面観でほぼ正三角形に収まる安定感のある立体構成、類型的ながら面貌表現や衣文表現にみられる抑制の利いた柔らかみのある彫り口等に正当な仏像彫刻技術の継承が認められる。この種の作風は江戸時代前期の彫刻に多く見られるもので、類例からすると延宝・元禄頃の彫刻に共通した特色が認められるところから、ひとまずその頃に位置づけておくことにしたい。
墨書銘にみえる浅草田原町の仏師三上喜八は、他にその名を聞いていない。仏師としてどのような技術と作風を持っていたのか不明である。
- 住所
- 横瀬町大字芦ヶ久保200
- 指定日・制定日
- 平成11年4月11日指定
- 管理者
- 総代 浅見清隆
文化財分類: 町指定有形文化財(彫刻)。
